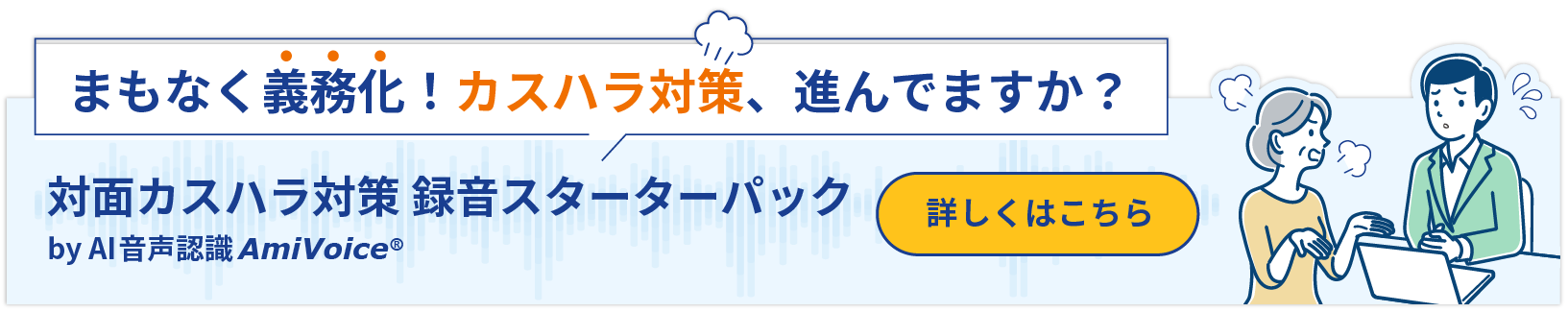カスハラとは?判断基準や事例・防ぐ方法や発生時の対処法を解説
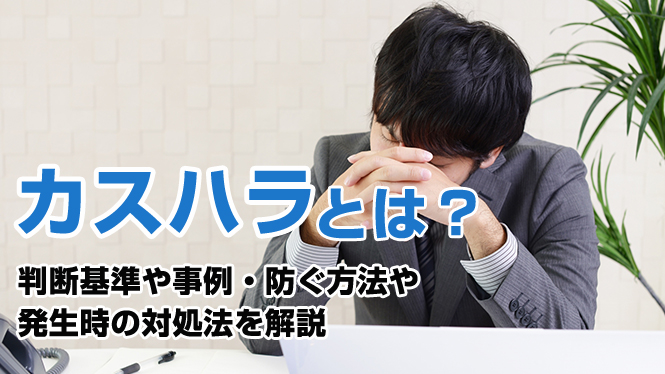
「お客様は神様」という言葉が昔はよく聞かれました。しかし近年では、一部の顧客による従業員への過度な要求や攻撃的な言動が問題視されており、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が生まれました。
カスハラは、職場におけるパワハラやセクハラと同様に、従業員の心身に大きな負担をかけ、働きやすい環境を破壊する深刻な問題です。当記事では、カスハラとは一体どのようなものなのか、具体的にどのような言動・行動がカスハラに該当するのか、カスハラを防ぐためにはどうすればいいかなどについて解説します。
1. カスハラとは
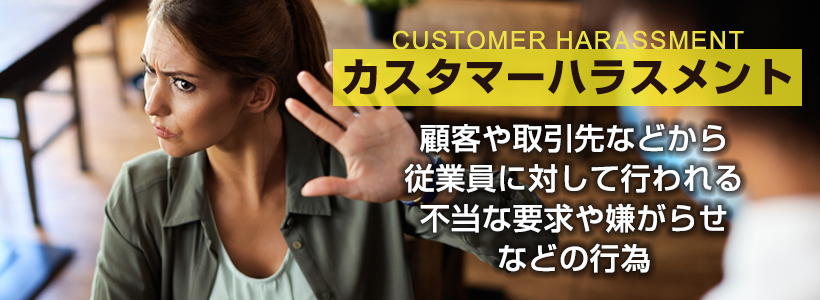
カスハラとは「カスタマーハラスメント」の略で、顧客や取引先などから、従業員に対して行われる不当な要求や嫌がらせなどの行為を指します。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では、以下のように定義されています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの
引用:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策マニュアル」引用日/2024/11/27
カスハラは、従業員の健康や企業の評判に大きなダメージを与える恐れがあります。企業は、カスハラ対策をしっかりと行い、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。
1-1. カスハラとなる言動の例
カスハラとなる言動の例はさまざまですが、以下に代表的なものをいくつか挙げます。
- 「お前は仕事ができない」「無能」など、従業員の人格や能力を否定するような言葉
- 「会社にクレームをつける」「訴訟を起こす」など、相手に恐怖を与える言葉
- 「今すぐやれ」「必ずしろ」など、一方的な命令
社会通念上不相当と考えられる過度な要求や脅迫などは、カスハラに該当する可能性が高いと考えられます。
1-2. カスハラとクレームの違い・判断基準
カスハラと正当なクレームとを区別するには、まず顧客の要求内容と手段を基準に判断します。
正当なクレームは、企業に何らかの過失があり、顧客の要求に妥当性が認められる場合です。商品やサービスの改善、問題解決が目的であり、具体的な事実に基づいた、改善を求める内容です。この場合、企業は事実関係を確認した上で、誠実に対応することが求められます。
一方で、カスハラは、顧客の要求に過度な主張や不適切な手段が含まれる場合です。例えば、長時間の説教やリピート型のクレーム、暴言・暴力、土下座の要求、SNSへの個人情報公開といった行為は、内容の妥当性に関係なく、社会通念に照らして不当とされます。従業員を苦しめたり、企業に損害を与えたりすることが目的になっており、企業は毅然とした対応をとる必要があります。
1-3. カスハラが注目される社会背景
「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員規模が100人以上の企業では、カスハラが「増加している」割合が「減少している」割合を上回っており、特に大企業でその傾向が顕著です。一方で、従業員規模99人以下の企業の場合、16.5%がカスハラが増加していると回答していますが、減少傾向(18.7%)も見られます。
出典:厚生労働省「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」
カスハラの増加の背景には、社会のサービス水準への期待の高まりや、顧客の権利意識の高まりが挙げられます。特にインターネットの普及によって、匿名での批判やレビューが容易に行える環境が整ったことで、顧客が店舗やサービスに対して厳しい要求を行うケースが増えています。特にSNSを通じた情報拡散力は非常に高いため、一度拡散された情報は消し去るのが困難です。
さらに、ストレス社会における心理的な圧迫や、パンデミック後の不安定な経済環境が、消費者のフラストレーションを増幅させている点も、不当なクレームに発展する要因と考えられています。
2. カスハラを放置すると企業が受ける悪影響
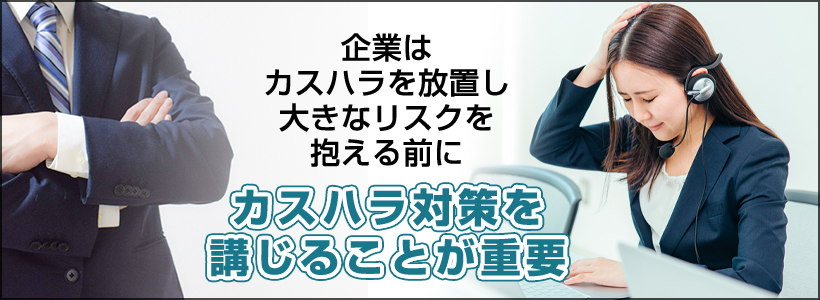
カスハラを放置した場合、企業は多くの悪影響を受けるため、大きなリスクを抱える前に、カスハラ対策を講じることが重要です。
カスハラを放置することによる具体的な悪影響としては、以下のような点が挙げられます。
2-1. 従業員のモチベーション低下や離職を招く
カスハラは、従業員に大きな精神的なダメージを与えます。暴言や侮辱、不当な要求などは、従業員を深く傷つけ、自己肯定感を大きく損なう可能性があります。また、カスハラが発生する職場は、心理的に安全な場所とは言えません。従業員は、常に不安や恐怖を感じながら仕事をしなければならず、集中して業務に取り組むことが困難になります。
他にも、会社がカスハラを放置しているという事実を知ると、従業員は会社への信頼を失い、所属意識が低下するでしょう。モチベーションが低下した従業員は、仕事への意欲が薄れ、ミスが増えたり、業務効率が低下したりする恐れがあります。
2-2. ブランドイメージの失墜や客離れが起きる
カスハラを放置することは、企業が従業員に対して適切な配慮を行っていないことを示す証拠となります。企業が社会的責任を果たしていないという印象を与え、企業イメージを大きく損なうことにつながるでしょう。また、カスハラ問題は、メディアに取り上げられやすく、一度炎上すると、その影響は長期間にわたって残る可能性があります。
顧客が離れていくことで、売上は減少します。特に、サービス業や小売業など、顧客との直接的な接点が重要な業界では、その影響は甚大です。
2-3. 企業が法的責任を問われる恐れがある
カスハラを放置すると、企業は法的責任を問われる可能性が高まります。
労働契約法では、企業は従業員に対して安全配慮義務を負っており、カスハラから従業員を守ることが求められます。もし、カスハラが発生し、企業が適切な対策を取らなかった結果、従業員が精神的なダメージを負った場合、企業は従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
さらに、労働施策総合推進法では、企業は職場におけるパワハラを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じる義務が定められています。厚生労働省が示す指針では、カスハラを「顧客等からの著しい迷惑行為」と定義し、企業が取るべき対策として、相談窓口の設置や被害者への配慮などが挙げられています。
つまり、カスハラを放置することは、法的な観点から見ても看過できない問題であり、企業は法的責任を問われるリスクを常に抱えていると言えるでしょう。カスハラによる法的リスクを回避するためには、事前に相談窓口を設置したり、従業員への教育を実施したりするなど、適切な対策を講じておくことが重要です。
※2025年6月に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会にて可決・成立し、今後カスハラ対策は雇用主の義務となります。
3. 実際に発生したカスハラの事例
カスハラは、サービス業を中心に、さまざまな業種で発生しており、カスハラの事例も多岐にわたります。以下では、実際に企業で発生したカスハラの具体的な事例を紹介します。
3-1. 大手鉄道グループの事例
JRにおいては、駅員や車掌など、対面でのサービス提供が多いことから、カスハラ被害に遭うケースが後を絶ちません。
例えば、JR西日本で発生したカスハラの事例として、精算機エラーに対応した駅員が「早くしろ!クズ!」と罵倒されたうえ、「殺すぞボケ!」と脅迫されたケースがあります。さらに、運転見合わせに対しても、乗客からしつこく詰問され、車掌がスマホで無断撮影されるというプライバシー侵害も起きました。
また、カスタマーセンターでは短時間に「殺すぞ」といった暴言が100回以上繰り返され、後に当該人物が逮捕された事件もあります。
これらの事例は、単なる不満の表明を超えた執拗な攻撃や暴言、脅迫行為が含まれており、対応する社員に対する精神的負担が大きい典型的なカスハラの事例です。
3-2. 介護施設の事例
介護施設で発生したカスハラの事例として、男性利用者が女性職員に対して性的な言動を行ったケースがあります。この利用者は、過去にも看護職員に物を投げつけたり、居室内で禁煙にもかかわらず喫煙したりするなどの問題行動が見られました。
今回の事例では、入浴介助中に利用者が自身の陰部を見せたり、職員の身体に触れたりするなどの不適切な行為を行いました。職員はすぐに管理者に報告し、管理者が利用者の居室を訪れ、今後の再発防止を求めました。利用者は「悪ふざけだった」と弁明しましたが、これもカスハラの事例の1つと言えるでしょう。
施設側は、利用者と担当職員が1対1で接触しないようシフトを変更し、今後は自立入浴を促す対応をとりました。
4. 企業がすべきカスハラ対策4選

カスハラに対する国や自治体の取り組みが本格化しています。
国では、従業員保護を目的としたカスハラ対策法案が進められており、企業に対しても適切な対応を求める法整備が検討されています。さらに、東京都では2025年4月から全国初となるカスハラ防止条例が施行されており、客の迷惑行為に対して事業者が従業員を守る責務を明確にしています。
これらの動きからも、企業は従業員を守るために、カスハラ対策を積極的に推進する必要性が高まっていると言えるでしょう。
4-1. カスハラ対策方針の制定
カスハラ対策方針とは、企業がカスハラを防止し、発生した場合には適切に対応するための基本的な考え方や行動指針をまとめたものです。組織のトップがカスハラ対策に強い関心を示し、率先して取り組む姿勢が重要です。
【カスハラ対策方針の例】
「〇〇株式会社は、すべての従業員が安心して働ける環境を整備するため、カスタマーハラスメントを許容しません。カスタマーハラスメントが発生した場合には、速やかに対応し、再発防止に努めます。従業員は、カスタマーハラスメントを受けた場合は、直属の上司または相談窓口に報告してください。会社は、被害にあった従業員を支援し、加害者に対しては適切な措置を講じます。」
上記はあくまで一例です。企業の規模や業種、従業員の構成など、自社の状況に合わせて、より具体的な内容に置き換えてください。
4-2. 相談窓口の制定・整備
カスハラを受けた従業員が安心して相談できる体制を作ることも大切であり、被害の早期発見と迅速な対応につながります。まず、企業は相談対応者を決め、専用の相談窓口を設置し、相談窓口の存在を従業員に広く周知することが重要です。これにより、従業員がどこに相談すればよいのか迷うことなく、速やかにサポートを受けられる環境が整います。
また、相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるよう、事前に専門的な研修やマニュアルを整備しておくことも必要です。
4-3. カスハラの対応手順の制定
カスハラの対応手順を具体的に制定することで、従業員が一貫性のある適切な対応を取れ、企業としてもリスクを最小限に抑えられます。
カスハラの対応手順として決めておくべき内容としては、以下の通りです。
報告体制
カスハラが発生した場合、誰が誰に報告するかを明確にします。発生日時、場所、内容、対応内容などを詳細に記録する、報告用のフォーマットも作っておくとよいでしょう。
初期対応の方法
被害者への対応、状況の把握、証拠の確保など、初期対応の手順を具体的に定めます。
関係部署への連絡
人事部、法務部など、関係部署への連絡手順を定めます。
外部機関への相談先
必要に応じて、弁護士、警察、労働基準監督署など、外部機関への相談窓口を明確にします。
カスハラに遭遇した際、現場の従業員がすぐに上司や専門チームにエスカレートできる体制を整備しましょう。
4-4. カスハラへ対処するルールの研修・教育
カスハラとは何か・どのように対応すべきかを、従業員全員が正しく理解することで、被害を未然に防ぎ、発生した場合も適切な対応ができます。
カスハラ研修・教育の目的の1つとして、カスハラに対する理解を深めることが挙げられます。従業員にカスハラの定義、種類、具体的な事例などを理解させ、カスハラを認識できるようにしましょう。カスハラが発生した場合の適切な対応方法を学び、冷静に対応できるよう訓練します。
5. カスハラが発生したときの対処方法
従業員に適切な教育をしていれば、カスハラが発生した場合でも、より円滑に対処できる可能性が高まります。以下では、カスハラが発生したときの対処方法について説明します。
5-1. 状況を正確に把握し共有する
カスハラが発生した際の初期対応は、後の状況を大きく左右します。まずは限定的に謝罪を行うこと、および状況を関係者に正しく共有することが大切です。
事実関係がまだ十分に把握できていない段階で、安易に謝罪してしまうと、企業側の責任を認めたと解釈される可能性があります。状況によっては、謝罪することでかえって相手を刺激し、事態を悪化させる場合もあるでしょう。「この度は、お客様にご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」といったように、具体的な行為ではなく、相手に不快な思いを与えてしまったことへの謝罪を表明します。
事実関係の確認においては、いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような言動があったのかを具体的に確認してください。
5-2. 顧客の言動を記録する
顧客の言動を記録することは非常に重要です。法的問題に発展した場合に備え、客観的な証拠として利用できます。録音や録画を行い、日時、場所、相手の名前、相手の言動、自分の対応、目撃者の有無などを記録しましょう。
現場で対応する際は、可能な限り2人以上で対応すべきです。万が一トラブルになった場合でも、企業側の証人となります。
5-3. 現場での対応可否を判断する
カスハラが発生した際、現場で対応できる範囲を超えるケースも考えられます。そのため、現場での対応可否を判断し、必要に応じて本社へエスカレーションするようにしてください。
まず、従業員はカスハラが発生した際に、顧客の要求や行動の性質を速やかに把握し、その場で解決可能な範囲かどうかを判断します。例えば、顧客の不満が商品の品質やサービス内容に関する軽い問題である場合、現場での解決が可能なケースが。
カスハラの内容が、現場の従業員やその場の責任者で対応できる範囲を超えている場合には、本社や上司へのエスカレーションを検討しましょう。例えば、「法的な対応が必要な状況や企業の方針を超える要求があった場合、警察との連携が必要になった場合などはエスカレーションする」など判断基準を伝えておくのも大切です。
5-4. 組織としての方針を顧客に通知する
企業はカスハラに対してどのような立場を取るのか、具体的な対応方針を明確にすることが必要です。従業員の安全を守ることを最優先とし、不当な要求や暴力的な行為には毅然とした態度で臨まなくてはなりません。
通知は、状況がエスカレートし、顧客が不合理な要求を続けたり、暴言や暴力行為に及んだりした際に行います。この際、従業員が冷静かつ明確な言葉で方針を説明し、必要な場合は書面で正式に通知しましょう。
5-5. 従業員の心身をケアする
カスハラを受けた従業員は、精神的なダメージを受け、仕事のパフォーマンス低下や離職につながる可能性があります。そのため、カスハラ発生時には、被害を受けた従業員の心身をケアすることが重要です。
必要に応じて、専門家(産業医、弁護士、精神科医など)と連携し、適切な支援を行いましょう。一度支援を行えば終わりではなく、長期的な視点でケアを行うことが大切です。
カスハラ対策にAmiVoice SF-CMSが活用できます
カスハラは、従業員はもちろん、企業や社会全体に大きな悪影響を与える深刻な問題です。企業は、従業員が安心して働ける環境を整備するためにも、カスハラ対策に積極的に取り組む必要があります。企業が対応を怠ると、労働基準法違反や安全配慮義務違反に該当する恐れがあり、法的責任を問われるリスクがある点にも注意しましょう。
アドバンスト・メディアが提供するAI音声認識サービス「AmiVoice SF-CMS」は、接客・商談・対面販売などで使える、スタッフと顧客双方の会話を全文テキスト化が可能なソリューションです。
顧客との会話をテキスト化しトラブル時のエビデンスとして活用するだけではなく、リアルタイムにリスク会話を自動検知してバックヤードにいるマネージャーや本部にアラート通知することも可能なため、カスハラなどのトラブル発生を即座に把握し、応対スタッフの早急なフォローを行うことも可能になります。
ご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
商談・接客のブラックボックス化を解消して、全社的な営業力強化を可能に
AmiVoice® SF-CMS のもっと詳しい内容は