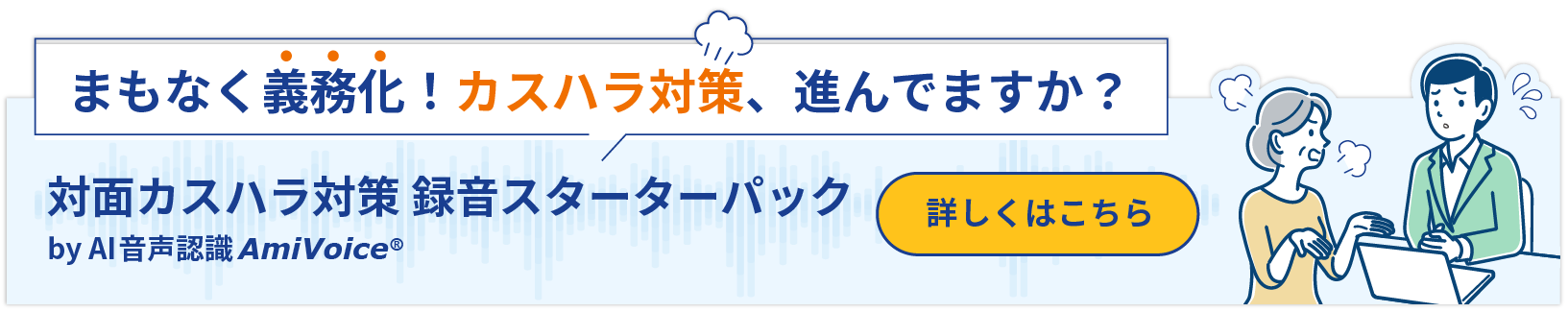カスハラ対策が法的に義務化!事例や企業の具体的な対策方法を解説!
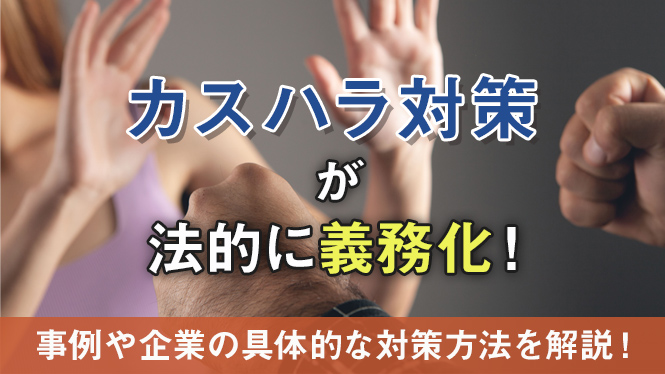
近年、社会問題として注目されているカスタマーハラスメント(通称:カスハラ)に対して、企業の法的責任が明確化されつつあります。
2025年6月に改正・労働施策総合推進法が成立し、2026年度中にはカスハラ防止が企業の義務として正式に施行される予定です。これにより、企業は従業員の就業環境を守るため、明確な方針の策定や相談体制の整備など、実効性ある対策を講じなければなりません。
当記事では、カスハラの実態や法改正の背景を解説しつつ、企業が講じるべき対策を具体的に紹介します。
1. カスハラ対策が法的に義務化!企業が対応すべき理由

2025年6月4日、改正・労働施策総合推進法が成立し、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が企業に義務付けられることとなりました。施行は2026年度中を予定しており、厚生労働省から具体的な指針が今後示される見込みです。
カスハラとは、顧客や取引先などが社会通念上許容されない言動を取ったことによって、労働者の就業環境が害される行為を指します。従業員を守るため、企業はカスハラを防止する体制を整備し、発生時には適切に対応する責任を負うことになります。
政府は、企業に対して「カスハラを許容しない方針の明確化と周知」「相談体制の整備」「発生時の迅速な対応」といった取り組みを求めています。また、顧客対応を担う従業員への研修や、マニュアル整備なども重要視されています。
今後、カスハラ対策は労働環境の安全確保として不可欠な経営課題となるでしょう。従業員のメンタルヘルスや職場定着率の観点からも、企業には早めの対応が求められます。
出典:厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
2. カスハラの実態とは?現場で起きた事例を紹介

カスハラ(カスタマーハラスメント)は、従業員の尊厳を脅かし、職場環境を著しく悪化させる深刻な問題です。法整備が進む背景には、現場で実際に起きている過剰な要求や暴言・威嚇行為の存在があります。
ここでは、業種別に報告されているカスハラの具体例を紹介します。
2-1. 宿泊業・飲食サービス業の事例
宿泊業や飲食サービス業は、接客の丁寧さが求められる業種であるがゆえに、顧客からの過剰な要求が発生しやすい傾向があります。
たとえば、宿泊のたびに客室の清掃不備を指摘し、執拗にグレードアップや目の前での清掃を要求するケースが報告されています。また、精算方法に不満を持った顧客が、「お前なんかクビにしてやる」「正座しろ」などの暴言を繰り返し、名刺を破るなどの威圧的な行動をとることもあります。
このような行為は、従業員の心理的負担を増大させ、業務遂行に深刻な支障を与えます。
2-2. 卸売業・小売業の事例
卸売業・小売業では、商品やサービスをめぐる理不尽な要求や暴力的な言動が目立ちます。
たとえば、プリペイドカードの返金を断ったところ、「店長を出せ」「返金しろ」と2時間以上にわたって詰問され、さらに本社への電話や来訪まで行われた事例があります。その他にも、接客態度への不満を理由に胸ぐらを掴まれ引きずられる、従業員の個人情報を要求される、深夜まで謝罪を強要されるといった悪質な行動も確認されています。
こうした行為は、従業員の心身に深刻なダメージを与えるだけでなく、業務全体の安全性や効率にも大きな影響を及ぼします。企業として、毅然とした対応と明確なルール整備が必要です。
2-3. 運輸業、郵便業の事例
運輸業や郵便業では、時間や交通に関するトラブルから、過剰な要求や暴力に発展するケースが後を絶ちません。
たとえば、運転見合わせ時の放送に納得しない旅客が車掌に詰め寄り、暴言や殺害予告に発展し、最終的に逮捕に至った例もあります。さらに、駅員に対して物理的暴力を加えたり、タクシー代の補填を繰り返し求めたりするなど、不当な要求も報告されています。
公共性の高いサービス業種であっても、従業員が一方的に我慢を強いられるべきではありません。事例からは、暴力・脅迫・名誉毀損に該当するような深刻な行為が多く含まれており、企業や行政による早急な対応が不可欠です。
3. カスハラ防止に向けた企業の具体的な対策方法
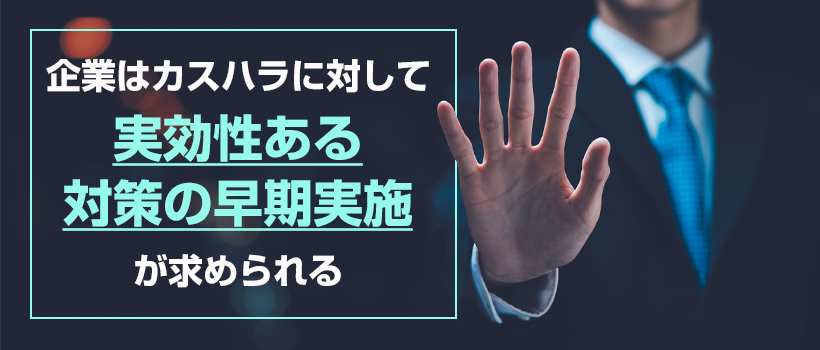
カスタマーハラスメント対策の強化が盛り込まれた労働施策総合推進法は2026年度中に施行が予定されています。企業はカスハラに対して、実効性ある対策の早期実施が求められます。ここでは、法的義務化に備えて企業が取り組むべき具体的な対策を紹介します。
3-1. カスハラを許さない姿勢を明確にする
カスハラ対策において最も重要なのは、「ハラスメントを容認しない」という明確な姿勢を企業のトップが示すことです。経営層が基本方針を打ち出し、従業員に向けて繰り返し発信することで、企業が従業員を守る意志を内外に示せます。
このような姿勢の明確化は、現場の従業員に安心感を与え、ハラスメント被害の報告や相談がしやすい職場環境の形成にもつながります。方針の表明は単なる形式ではなく、従業員の心の支えとなる実効的な手段です。
3-2. 日頃から顧客と対等な関係を築く
過剰な「顧客第一主義」は、従業員を不当な要求にさらす温床になりかねません。カスハラを防ぐには、顧客と対等な関係を築く意識が必要です。
また、対応する従業員自身も、無理な要求に屈しない心構えとスキルが求められます。アンガーマネジメントの理解やロールプレイによる訓練は、冷静な対応力の向上に役立ちます。
3-3. カスハラ対応マニュアルを整備する
カスハラを未然に防ぎ、発生時に適切に対応するためには、具体的な対応マニュアルの整備が不可欠です。効果的なマニュアルの作成には、実際の事例を数多く収集し、ケース別の対処方法や判断基準を明確に記載する必要があります。
内容は定期的に更新し、現場の声を反映することが実用性を高めるポイントです。また、「カスハラが発生したときは複数人で対応する」「管理者が現場に出る」といった体制上のルールも併せて盛り込み、属人的な対応に依存しない運用体制を構築しておきましょう。
3-4. クレームとの違いを明確にする
カスハラ対策を講じる上で重要なのは、正当なクレームとカスハラにおける悪質なクレームを明確に区別することです。
正当なクレーム自体は商品やサービスの改善に活用できる有益な意見であり、誠実に受け止める必要があります。一方で、執拗な要求や理不尽な言いがかりといった行為は、従業員の精神的負担を増大させ、通常業務にも悪影響を及ぼします。
組織として悪質なクレームに対する判断基準を明文化し、従業員が対応に迷わない体制を整えることが、健全な顧客対応の実現に不可欠です。
3-5. クレーム内容を社内で迅速に共有する
カスハラ発生時の適切な初動対応には、現場での相談受付と社内での迅速な情報共有が不可欠です。相談対応者は、被害を受けた従業員や目撃者から状況を確認し、必要に応じて録画・録音などの客観的記録を用いて事実確認を行います。その上で、関係部署と連携しながら、顧客への対応方法を検討し、被害を受けた従業員へのフォローも行わなくてはなりません。
通常のクレーム対応と一体化させた手順を整備しておくことで、現場は混乱せず一貫した対応が可能となります。
3-6. カスハラ対策を学ぶための研修を行う
カスハラ発生時に適切な対応を取るには、事前の研修を通じた実践的な知識とスキルの習得が必要です。マニュアルを読んで理解するだけでは感情的な顧客への対応は難しいため、ロールプレイやケーススタディを活用し、対応経験を積ませることが効果的です。
研修内容には、クレームとカスハラの違いや、判断が難しい事例への対応方法、論理的な伝え方(ロジカルコミュニケーション)、ストレスに耐えるレジリエンス力などを盛り込むとよいでしょう。研修を通じて従業員の自己判断力を高めることで、企業全体の対応力向上につながります。
3-7. 社員がすぐに相談できる体制を整える
カスハラへの迅速な対応には、従業員が安心して相談できる体制の整備が不可欠です。相談窓口を明確に設け、被害が発生した場合だけでなく、「該当するか分からない」という段階でも気軽に相談できるよう、社内での周知を徹底しましょう。
相談対応者には、現場の管理監督者や上司など、日常的に従業員と接している人物が適任です。さらに、人事や法務部門、外部の専門家との連携体制を構築し、マニュアルや研修制度を整えることで、より実効性のある相談体制が確立できます。
カスハラ対策にはSF-CMSが活用できます
カスハラへの法的対応が求められるなか、企業には一過性の対処ではなく、継続的で組織的な取り組みが期待されています。カスハラ対策として、マニュアル整備や社員研修の充実だけでなく、日々の対応内容を記録・分析し、再発防止や組織全体の対応力強化につなげる取り組みが不可欠です。
カスハラを防ぐために、音声認識市場国内シェアNo.1※の株式会社アドバンスト・メディアが提供する 「AmiVoice® SF-CMS」は非常に有効です。対面接客シーンでの会話をすべて記録・テキスト化し、データを蓄積できるだけでなく、必要に応じて担当部署にリアルタイムでヘルプ通知を送信することも可能です。現場の声を見える化し、証拠保全と迅速な対応を支援するツールとして、カスハラ対策の実務を支える強力な選択肢と言えるでしょう。
※合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場