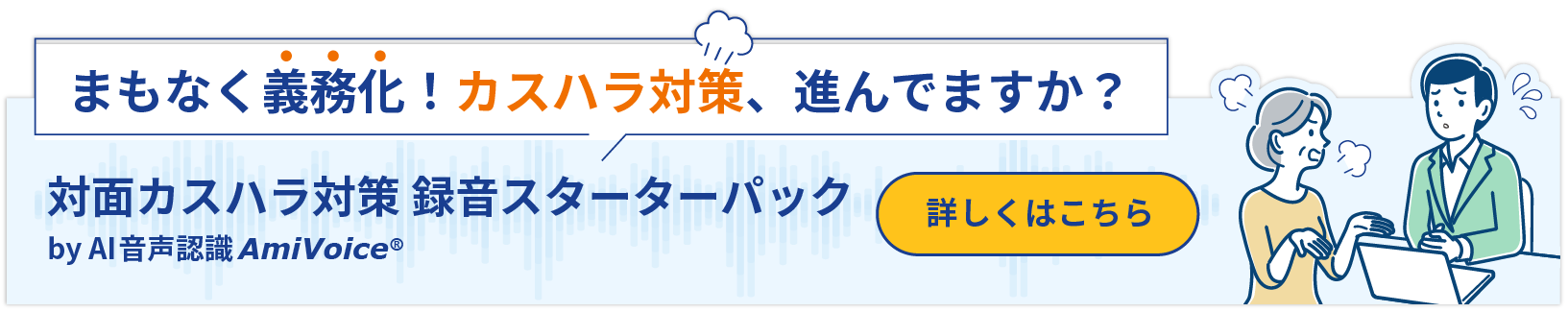カスハラ防止条例とは?条例の規定内容・罰則・自治体の事例を解説!
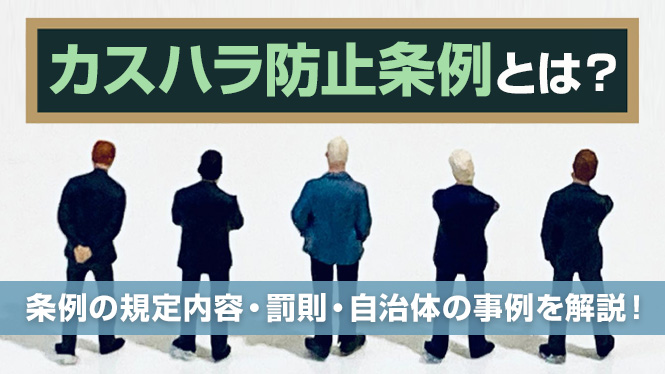
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、従業員への暴言や過剰なクレームなどを指し、深刻な社会問題となっています。こうした背景から、東京都では2025年にカスハラ防止条例が施行されました。
当記事では、条例の基本方針や定義、対象者の範囲を解説するとともに、北海道や三重県桑名市など、他の自治体での取り組みにも触れます。カスハラ対策に役立つシステム導入のヒントも紹介しますので、働く人を守る環境づくりに関心のある方は、ぜひご覧ください。
1. カスハラ防止条例とは

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客から従業員に対して行われる著しい迷惑行為のことを指します。こうした行為から就業者を守るため、東京都では全国で初めて「カスハラ防止条例」が制定されました。
この条例では、「何人もカスハラを行ってはならない」と明記されており、事業者や顧客の双方に防止の責務が課されています。罰則こそ設けられていないものの、働く人の安全や健康を守り、持続可能で公正な社会の実現を目指す取り組みです。現在では、北海道や群馬県など他の自治体にも広がりを見せています。
1-1. カスハラ防止条例の施行はいつから?
東京都のカスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行されました。条例の公布は2024年10月、指針の策定は2024年12月で、事業者・顧客双方が守るべきルールと具体的な対処例が示されました。他自治体でも施行時期がほぼ同時期に集中しています。
さらに、2024年12月には「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が策定され、具体的な対応例や対処法も示されました。条例とガイドラインの両面から、働く方の安心と消費者の適切な行動のバランスを目指しています。
2. 東京都カスハラ防止条例の概要
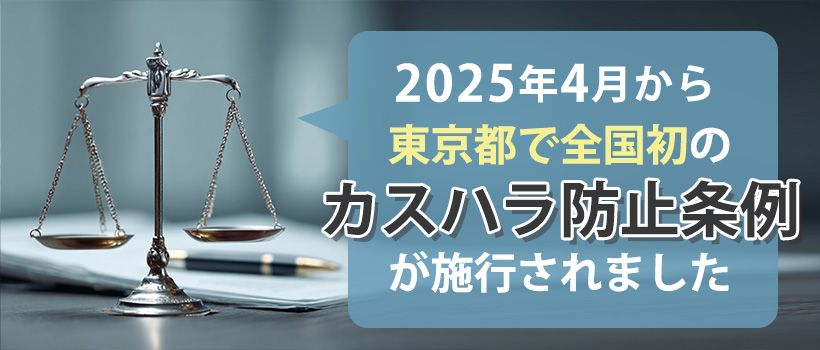
東京都で全国初となるカスハラ防止条例が制定され、2025年4月から施行されました。この条例では、働く人の安心と健全な消費活動を守るための基本方針や、カスハラの定義、対象者の範囲などが具体的に定められています。ここでは、その内容を3つの視点から詳しく解説します。
2-1. 条例の基本方針となる3つの柱
東京都が公開している「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」では、カスハラ防止の枠組みとして、以下の3つの柱が明示されています。
- 「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として、カスタマーハラスメントの禁止を規定
- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定
- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定
引用:東京都「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」引用日2025年7月10日
東京都のカスハラ防止条例では、禁止の明文化、関係者ごとの責務、指針による支援体制の整備という3本の柱が定められています。これにより、「誰もカスハラをしてはならない」という明確な姿勢が示されるとともに、都や事業者・顧客を含めた全体の連携が求められています。指針に基づく研修や相談体制などの支援が用意され、現場での実効的な対策が進めやすくなることが期待されています。
2-2. カスハラとは何か?条例における定義
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、東京都カスハラ防止条例において「顧客等から就業者に対し、その業務に関連して行われる著しい迷惑行為であり、就業環境を害するもの」と定義されています。ここでいう「著しい迷惑行為」には、暴力や脅迫といった違法行為だけでなく、正当な理由のない過度な要求や暴言なども含まれます。
たとえば、繰り返される過剰なクレームや土下座の強要、名札の無断撮影・SNS投稿などが該当する可能性があります。これらの行為が、働く人の身体的・精神的苦痛を生み出し、業務の継続に支障を与える場合には、社会全体で対応すべき問題として位置づけられています。
2-3. 誰が対象になる?事業者・就業者・顧客の意味
カスタマーハラスメント防止条例では、「事業者」「就業者」「顧客等」の三者を対象としています。それぞれの立場と該当する例を正しく理解することで、条例の対象や責任の所在を明確にできます。以下では各定義と具体例を紹介します。
■事業者
都内で営利・非営利を問わず事業を行う法人・団体・国の機関・個人を指します。
- 都内に本社のある企業
- 都外に本社があるが、都内に支店がある企業
- 都内の官公署
- 都内で事業を行う個人事業主
■就業者
事業者の業務に従事するすべての人です。有償・無償や雇用形態を問わず対象です。
- 都内の企業に勤務する従業員
- 都外勤務だが、都内企業の業務に関わる人
- 地域の清掃活動などに従事するボランティア
■顧客等
就業者から商品やサービスの提供を受ける人、またはその業務に密接に関わる人です。
- 商品を購入する客
- 公共施設を利用する市民
- クレーム処理対応の際に関わる第三者
3. 各自治体のカスハラ防止条例の動き|罰則の有無も
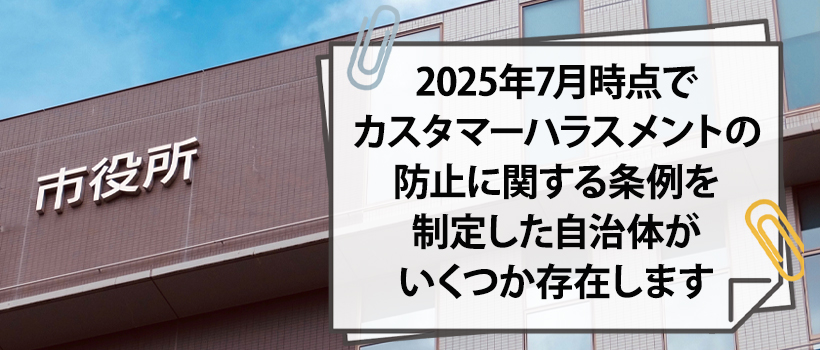
2025年7月時点で、カスタマーハラスメントの防止に関する条例を制定した自治体がいくつか存在します。ここでは、それぞれの自治体の取り組みや特徴、罰則の有無について解説します。
3-1. 北海道
北海道では、2024年11月29日に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」を公布し、2025年4月1日に施行しました。全国で初めて議員提案により成立したカスハラ防止条例であり、罰則規定は設けず、今後の法整備の動向を踏まえて3年以内に見直す方針です。
出典:朝日新聞「カスハラ条例成立、議員提案としては初めて 来年4月に施行 北海道」
条例では、事業者や就業者だけでなく、道民にもカスハラへの理解促進を求める努力義務を課しているのが特徴です。また、道・市町村・事業者などが連携して課題に取り組む「協議会」の設置も定められています。典型事例の明示、相談体制の整備、人材育成など、多方面からの支援が盛り込まれた包括的な内容となっています。
3-2. 三重県桑名市
三重県桑名市では、2024年12月25日に公布、また2025年4月1日に全国初となる氏名公表の制裁規定を含むカスタマーハラスメント防止条例を施行しました。条例では、カスハラ行為が繰り返され、市の警告を経ても改善が見られない場合、行為者の氏名等が公表されます。この制裁には、相談受付・審議・警告・意見聴取などの厳格な手続きを経る必要があると定められています。
出典:桑名市「STOPカスハラ カスタマーハラスメントの防止に関する指針」
出典:NHK「桑名市で「カスハラ防止条例」施行 相談窓口を設置 三重」
また、市内の事業者でカスハラ被害に遭った就業者に対し、最大10万円の補助金を支給する制度も設けられ、被害者支援にも力を入れています。市役所には専用の相談窓口が設置され、電話・対面・Webでの受付にも対応しています。
3-3. 群馬県
群馬県は、2025年3月27日にカスハラ防止条例を公布し、4月1日に施行しました。都道府県としては全国3例目となります。罰則はありませんが、県・事業者・就業者・顧客それぞれに責務が課されているのが特徴です。
県は啓発・教育・支援情報の提供などを行い、必要に応じて財政的支援にも努めるとしています。事業者には研修や顧客への啓発、就業者には協力と理解、顧客には節度ある言動が求められます。また、顧客の正当な権利を損なわないよう配慮することも明記され、バランスに配慮された内容となっています。
3-4. 群馬県嬬恋村
群馬県嬬恋村では、2025年3月4日にカスハラ防止条例を公布し、4月1日に施行しました。村議会で可決された条例で、村としての責務も明記されている点が特徴です。
条例では、顧客・事業者・従業員が協力して防止に努める基本理念を掲げつつ、村も啓発や情報提供などの支援を行う立場として位置付けられています。また、就業者がカスハラを受けた場合には、事業者が配慮と適切な対応を行う責務も定められました。小規模自治体における先進的な取り組みとして、注目されています。
カスハラ対策にはSF-CMSが活用できます
カスハラ防止条例は東京都が全国初となる制定を行い、2025年4月から施行されました。北海道、群馬県、三重県桑名市、群馬県嬬恋村でも続々と制定され、全国的な広がりを見せています。条例では事業者、就業者、顧客それぞれに責務が課され、カスハラの定義や対象者の範囲が明確化されました。桑名市では氏名公表という制裁規定も設けられ、より実効性のある対策が講じられています。
こうしたカスハラ対策には、被害の客観的な記録と証拠保全が重要です。音声認識市場国内シェアNo.1※の株式会社アドバンスト・メディアが提供する「AmiVoice® SF-CMS」なら、対面接客シーンでの顧客との会話をすべて記録・テキスト化できます。データはクラウドに保存されるため、リモートからでも円滑にカスハラの事実確認や事後対応が進められます。 また、問題発生時にはマネージャーや担当部署にヘルプ通知を送ることで、迅速な対応と組織的な支援体制の構築が可能になります。
※合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場